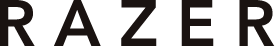- TOP-
- MAGAZINE

コロナが落ち着いてきた!?社員の会食や会合をどこまで容認したらよいか?
2020.10.19
今必要な危機管理広報・危機管理広報
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
2020年5月末に日本全国で緊急事態宣言が解除されてから、
最近(10月19日現在)ではGo Toトラベルを利用して、旅行に行く方も多くなってきました。
コロナ危機が完全に収束したとはいえませんが、感染者数の推移も一定数を保ちつつあります。
働く皆さんにとっては、約半年ほど慣れないリモートワークや自粛期間などを経て、外に出たい気持ちが募っている方も多いと思います。
そんな中、広報や総務の方から相談が増えているのは、
”コロナは少しだけ落ち着いてきた感じだけど、会社として社員の会合やお客様との会食をどこまで容認、規制したら良いかわからない”
いう内容です。
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image="768" img_size="full" alignment="center"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
例えば、ある顧問先では下記のように
危機レベルを下記の3段階に分けて(BCPに基づく)社員が今は何がNG行動なのか迷わないように明確にしています。
レベル3:【緊急事態宣言発動】 顧客との会食禁止、社員同士の会合禁止
レベル2:【1日の感染者数XXX人以上】 顧客との会食は禁止、社員同士の会合は5名以内、事前に届出提出が必要
レベル1:【緊急事態制限解除】 顧客との会食は5名以内で原則個室のある飲食店で行う、社員同士の会合は8名以内で記録を残す義務
レベル0:【会社よりレベル0の通達】規制なし
またレベルに応じて、リモートと出社のローテーションなどレベル別のシフトや会議室の使用規定など、
社員が判断に迷うと想定できることは細かく決めておくと更によいでしょう。
ただ結論からいうと、このようなご相談に対して、
「正解はありません。
だから安心して方針を立てて、積極的に情報発信してください。
大事なことは、コロナや今後の正解を会社がどう定義し、それに対しどこまでの対策するか決めることです。
そして決めたことを適切にステークホルダーに情報開示し、コミュニケーションを重ねることが重要です。
そして対策が間違えて、万が一感染者が出てしまったら、その事実を真摯に受け止め、
軌道修正(再発防止策を立てる)を行い再定義と対策を繰り返すことが大切です。」
とお答えし、必要に応じて危機管理機能がある部署の方と実際にやりとりをはじめます。
方針は会社の規模や業種によって異なってよいのです。
プラス
「社員が自粛疲れや不安な気持ちになっているケースが多くなっているので、
もし出来れば対策方針とともに、万が一社員が感染しても会社として、
差別や責めたりしない姿勢というメッセージも社内向けに発信されてはどうですか?」
とお伝えしています。
実際に社員向けのメッセージを代表自ら配信した会社では、結果的に社員のエンゲージメントが高まったとうれしいフィードバックをいただきます。
厚生労働省の「新しい生活様式」の実践例では、
・人との感覚はできるだけ2m(最低1m)あける
・会話をするときは真正面を避ける
とあります。
実践例に沿った行動をとることは、経済活動において現実的ではないケースもあります。
事業を行うということは、大なり小なりリスクをとることです。
会社がどこまで危機管理を行うか方針を決めることは、
健全な経営に欠かせない、これからの時代に必要な行動だと思います。
GMOインターネットは、まだ世間がコロナ危機が自分ごとになる前の2020年1月にいち早く在宅勤務を導入しました。
BCPの準備と訓練が奏功し、業務生産性はほとんど下がっていないと日本経済新聞のインタビューで答えています。
他の企業のお手本になるような、素晴らしい対応だと思いました。
これからの時代は広報担当者がBCPについて理解をしておく必要があると同時に、
危機管理本部や総務担当の方が広報機能を兼務する必要があると思いました。
朝日新聞社が実施した世論調査でGo Toトラベルでは
評価するが「47%」、評価しないが「43%」(10/17,18調査)
読売新聞の世論調査では、政府のこれまでの対応は
適切が「48%」適切でないが「44%」、
評価するが「56%」、評価しないが「37%」でした。(10/16〜18調査)
どんな対策を講じても、いつも時代も世間の評価は賛否両論なものです。
過剰な心配をして萎縮せず、方針を決めたら後は堂々としましょう。
そして常に社内を含め、ステークホルダーとの対話を怠らないように、
このような時代だからこそコミュニケーションを積極的に行うことが大切だと思います。
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][vc_column][vc_zigzag el_width="10"][vc_column_text]
最後に
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]「まず、何から始めたらいいですか?」という声は、初めてお問い合わせ頂いたお客様からのご相談でよく頂きます。
少しでもこのマガジンを読んでいただいている方の、危機管理広報のファーストステップのきっかけになれたら嬉しいです。当社はBCP作成やレビュー、社内研修、勉強会の開催などもサポートさせて頂いております。ご興味がおありでしたら、ぜひお問い合わせください。[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]<レイザー株式会社 お問い合わせ>
お電話でのお問い合わせ: 03-5953-7008
(営業時間 9:00〜18:00 /土日祝除く)
フォームでのお問い合わせ:https://form.run/@razer
危機管理広報トレーニングプログラム「KIKI(キキ)」は、企業が万が一の時に対応できるよう、体制構築、マニュアルの整備、トレーニングなどの訓練をサポートするプログラムです。詳細は下記のバナーをクリック!↓↓↓[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image="269" img_size="full" onclick="custom_link" img_link_target="_blank" link="https://crisispr.jp/"][/vc_column][/vc_row]
CONTACTお問い合わせ
-
お電話でのご相談
営業時間 平日9:00〜18:00 / 土日祝除く
-
フォームでのご相談
必要事項を入力の上、フォームよりお問合せください。
担当者より折り返しご連絡させていただきます。
営業時間外の場合、翌営業日以降のご連絡となります。